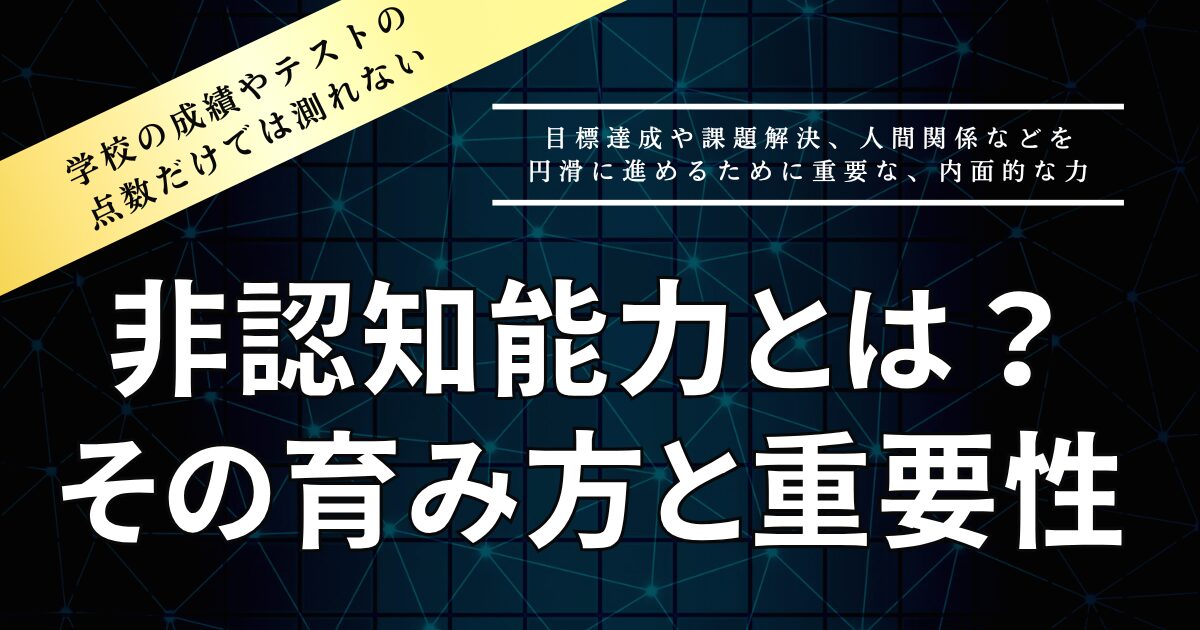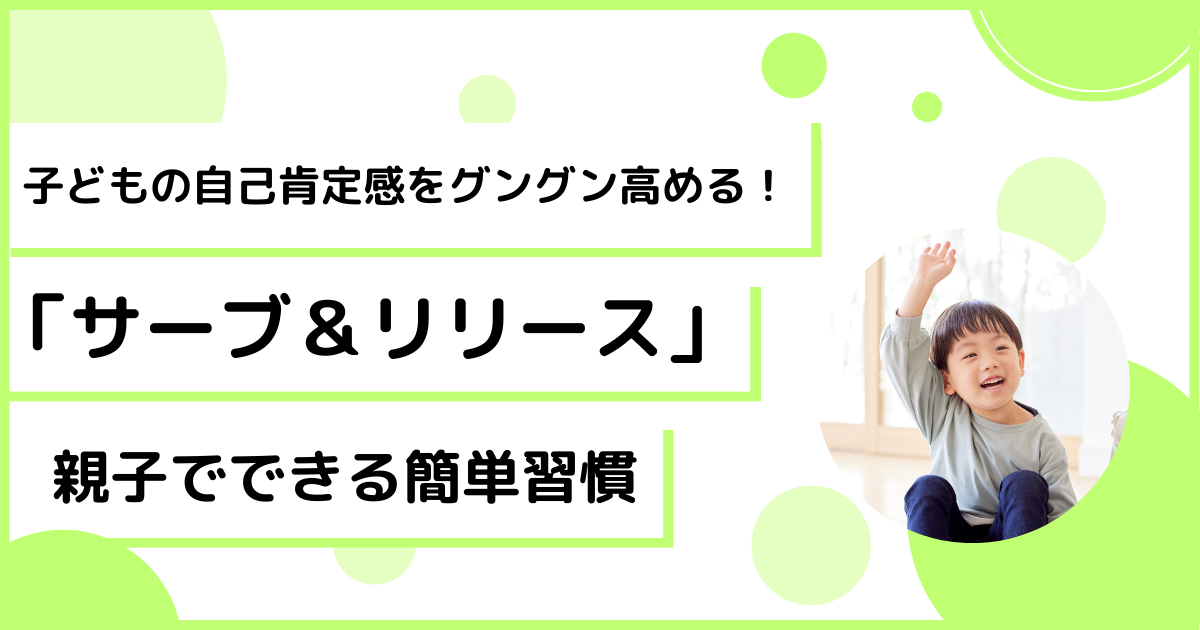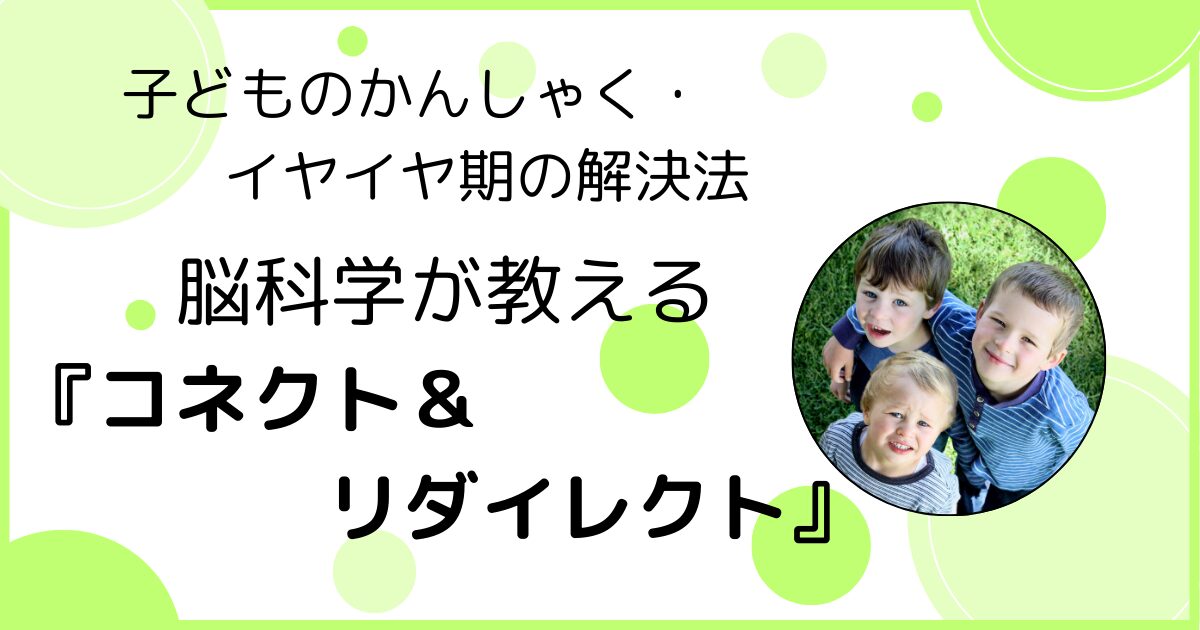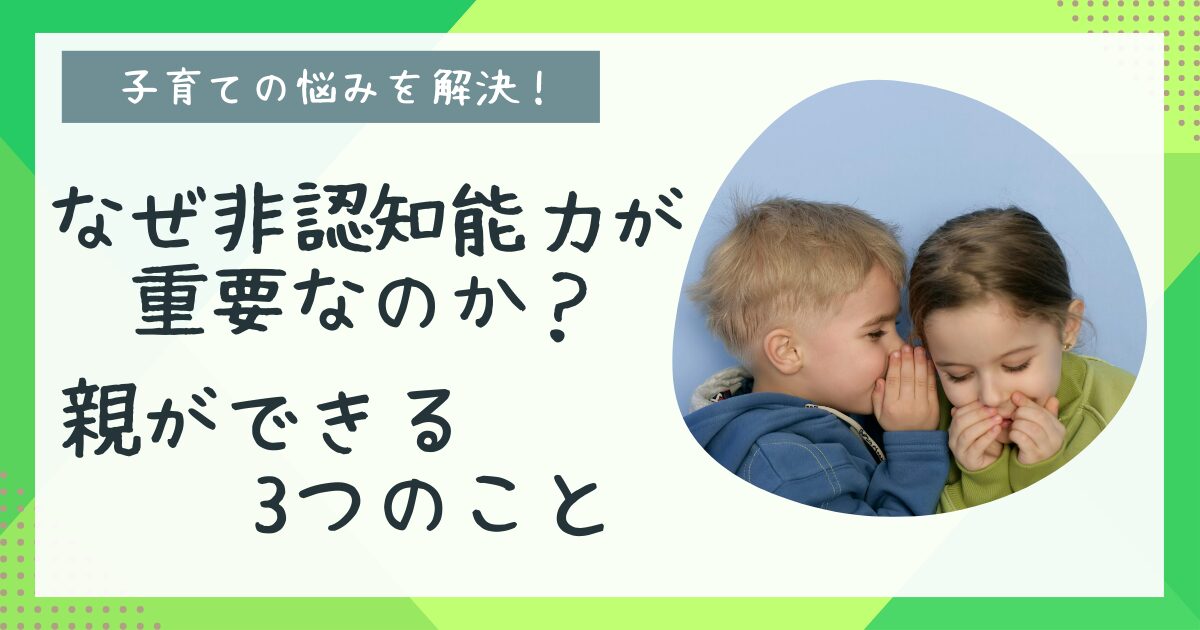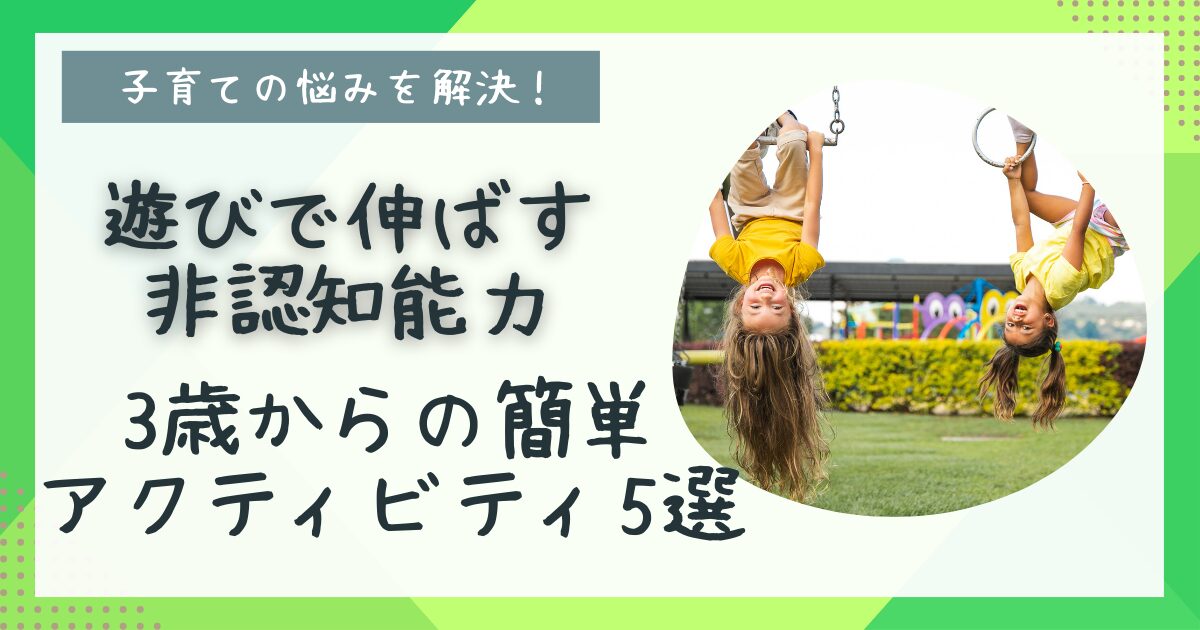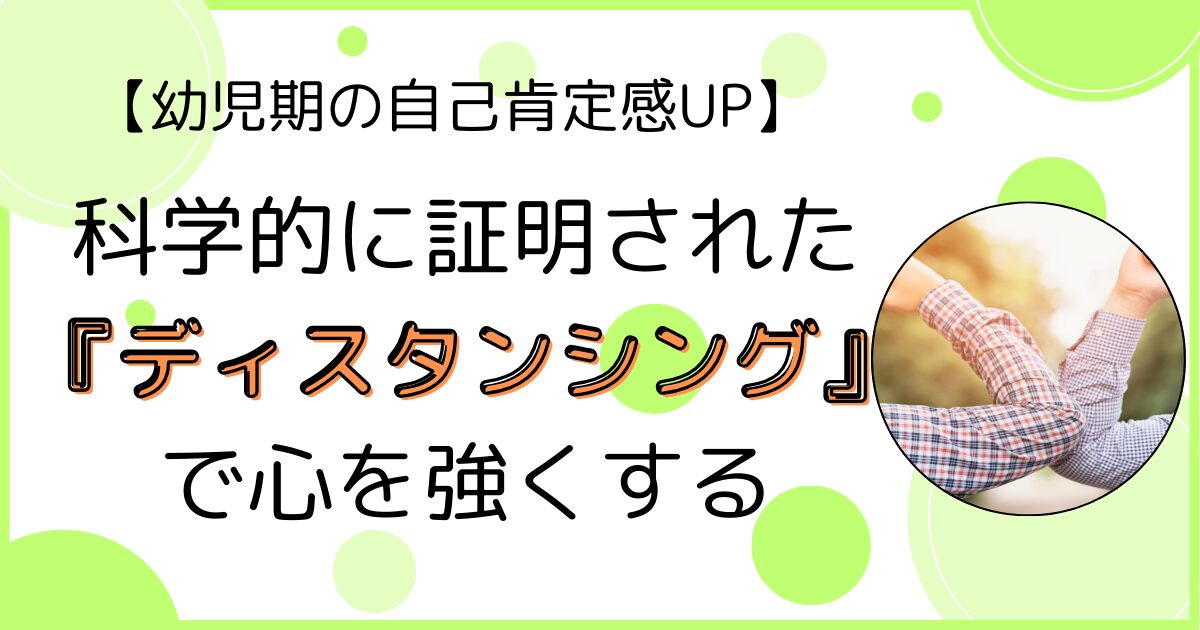
「うちの子、すぐに『もうダメだ…』って言うんです…」
「失敗すると、すぐに泣き出しちゃうんです…」
子育てをしていると、子どもがネガティブな感情に振り回される姿を目にすることがあります。
「失敗を怖がる」
「挑戦を避ける」
「すぐに諦める」
—— こんな姿を見ると、親としてはどう対応すべきか悩みますよね。
実は、幼児期(2歳~6歳)は自己肯定感の土台が作られる大切な時期。
この時期に、子どもが自分の感情とうまく向き合えるようになることは、将来の心の健康に大きく影響します。
この記事では、科学的に証明された心理学的手法『ディスタンシング』を活用し、子どもの自己肯定感を高める具体的な方法を紹介します。
1. ディスタンシングとは?

ディスタンシングとは、自分の感情や思考を客観的に捉える心理学的手法です。
例えば、次のような方法で「感情と自分を切り離して考える」ことで、冷静な視点を持てるようになります。
✅ 自分の気持ちを「雲」に例える(感情を視覚化)
✅ お人形やキャラクターになりきって考える(第三者視点)
✅ 自分の名前を使って話す(自己を客観視)
この手法は、認知行動療法(CBT)やマインドフルネス認知療法(MBCT)など、科学的根拠に基づいた心理療法でも活用されています。
(参考文献: Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press.)
2. なぜ幼児期にディスタンシングが重要なのか?

幼児期は感情のコントロールが難しい時期
幼児の脳はまだ発達途中で、特に感情をコントロールする前頭前野が未熟です。
そのため、ちょっとしたことで「もうダメだ…」と感じやすく、ネガティブな感情に流されやすいのです。
ディスタンシングの効果
ディスタンシングを学ぶことで、子どもは次のような力を身につけることができます。
✅ 自分の感情に気づき、整理できる
✅ ネガティブな感情に振り回されなくなる
✅ 「どうすればいいかな?」と考えられるようになる
✅ 失敗を乗り越える力(レジリエンス)が育つ
「自己肯定感」は、「失敗しても大丈夫」「やり直せばいい」と思える力が土台となります。
ディスタンシングを使って「気持ちを整理する力」を育てることで、子どもが自分に自信を持ち、挑戦を楽しめるようになるのです。
3. 親子で実践!ディスタンシングを使った4つの自己肯定感UP法

1. 感情の可視化:気持ちの雲を描こう!
📝 方法
- 画用紙に、その日の気持ちを表す雲の絵を描く。
- 「嬉しい時は、ふわふわの白い雲」「悲しい時は、ポツポツ雨降りの雲」など、色や形で表現する。
- 「雲はずっと続かないよ」と伝え、感情は一時的なものだと理解させる。
💡 なぜ効果的?
感情を視覚化することで、子どもは自分の気持ちを客観的に捉えやすくなります。
感情に名前をつけ、形を与えることで、冷静に向き合えるようになります。
2. 視点の転換:お人形さんに聞いてみよう!
📝 方法
- 困ったことがあったら、お人形やぬいぐるみに「〇〇ちゃん、どうしたの?」と聞いてみる。
- 子どもが答えられない場合は、親が代わりにお人形の声を演じる。
- 「じゃあ、お人形さんならどうする?」と問いかけ、解決策を一緒に考える。
💡 なぜ効果的?
自分の感情を第三者の視点から見ることで、客観的に分析する力がつきます。
3. 「魔法の言葉」で自己肯定感UP!
📝 方法
- 子どもが落ち込んでいたら、「大丈夫!〇〇ちゃんなら、きっとできるよ!」と声をかける。
- 同時にハグや手を握るなどのスキンシップをとる。
- 何度も繰り返し伝え、子ども自身が「大丈夫!」と言えるようにする。
💡 なぜ効果的?
ポジティブな言葉かけは、子どもの「自己肯定感」を育む鍵になります。
また、身体的な接触は、安心感を与え、ネガティブな感情を和らげる効果があります。
4. マインドフルネス:親子で深呼吸タイム
📝 方法
- 静かな音楽をかけ、親子でゆっくり深呼吸をする。
- 目を閉じ、鳥のさえずりや風の音など、周りの音に耳を澄ませる。
- 「今この瞬間に集中する」ことを意識する。
💡 なぜ効果的?
マインドフルネスは、ストレスを軽減し、感情を落ち着かせる効果があります。
4. ディスタンシング実践のポイント

✅ まずは子どもの気持ちに寄り添う(「そうだったんだね」と共感する)
✅ 焦らず、少しずつ取り入れる(最初から完璧を求めない)
✅ 遊びを通して楽しく実践する(無理にやらせない)
5. まとめ
ディスタンシングは、子どもの自己肯定感を高め、心の成長を促す有効な手段です。
親がそばで「一緒に考えよう」と寄り添うことで、子どもは安心して感情と向き合うことができます。
🌱 今日から親子でディスタンシングを実践し、子どもの「もうダメだ…」を「やってみよう!」に変えていきましょう! 😊