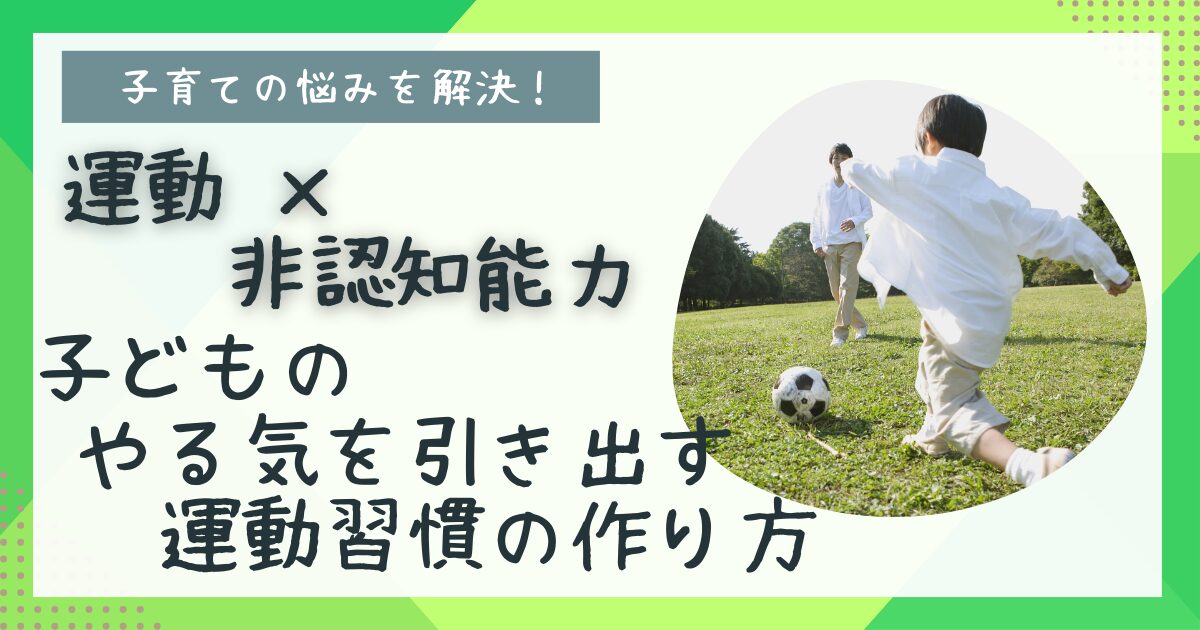
1. はじめに
「最近の子どもは運動不足」とよく言われますが、実際に文部科学省の調査(2022年)によると、小学生の体力テストの平均点は過去10年間で低下傾向にあります。特に、新型コロナウイルスの影響による外遊びの減少などが、子どもたちの運動習慣に影響を与えていると指摘されています。
一方、OECDのPISA調査(2022年)では、日本の15歳の読解力が過去最高の3位に上昇しました。しかし、学力が高い一方で、ストレスや不安を感じる子どもが増えていることも報告されており、心と体のバランスを取ることの重要性が改めて注目されています。
近年の脳科学の研究では、運動が脳の発達を促し、学習意欲ややる気の向上に大きく貢献することがわかっています。また、運動を通じて「努力する力」「失敗を乗り越える力」などの非認知能力を育むこともできます。
では、どのように運動を取り入れれば、子どものやる気を引き出し、非認知能力を伸ばすことができるのでしょうか?
この記事では、運動を通じて子どものやる気を引き出し、非認知能力を育む方法を、年齢層別に詳しく紹介します。
2. 運動が子どものやる気を引き出す理由

運動が脳に与える影響
- セロトニン: 精神を安定させ、不安やストレスを軽減する
- ドーパミン: 快感や意欲を司り、目標達成や課題克服へのモチベーションを高める
運動をすると、これらのホルモンが分泌されるため、子どもはポジティブな気持ちになり、やる気が湧いてくるのです。
脳科学の研究が示す運動の重要性
運動が脳に与える影響については、様々な研究が行われています。
例えば、ハーバード大学の研究では、運動によって脳の神経細胞の成長を促す物質の分泌が促進されることや、脳の特定部位の活性化が認められることなどが報告されています。
カリフォルニア大学の研究では、毎日20分の運動を行う子どもは、運動をしない子どもに比べて記憶力テストの成績が約20%向上したという結果もあります。
これらの研究成果は、運動が子どもの脳の発達に良い影響を与える可能性を示唆しています。
3. 運動が子どもの非認知能力を育む効果

運動をすると、以下のような非認知能力が自然と育まれます。
- 目標設定力 → 「縄跳びで10回跳べるようになろう!」と目標を立てる
- 問題解決能力 → 「どうすれば早く走れる?」と試行錯誤する
- 協調性 → チームスポーツで仲間と協力する経験を積む
- 自制心 → ルールを守り、感情をコントロールする力を養う
- 忍耐力 → 失敗しても諦めずに挑戦し続ける力が育つ
- レジリエンス(回復力) → 失敗や挫折を経験しながら立ち直る力がつく
特に、レジリエンス(回復力)は、子どもの将来の成功に大きく影響すると言われています。
運動を通じて、「失敗してもまた挑戦する」経験を積むことで、ストレス耐性が鍛えられるのです。
4. 年齢別!家庭でできる運動習慣の作り方

幼児期(3~5歳)
おすすめ運動: 公園遊び(鬼ごっこ、ボール遊び)、親子体操、簡単なダンス
ポイント:
- 「楽しい!」を最優先 → 遊び感覚で体を動かす習慣をつける
- 親も一緒に動く → 一緒にやることで継続しやすい
学童期(6~12歳)
おすすめ運動: 縄跳び、サッカー、バスケ、スイミング、ダンス、鬼ごっこ
ポイント:
- 目標設定をする → 「1分間で〇回縄跳び!」など小さな目標を設定
- チームスポーツを取り入れる → 協調性・コミュニケーション能力を養う
思春期(13歳~)
おすすめ運動: ジョギング、サイクリング、ヨガ、部活動、筋力トレーニング
ポイント:
- 「健康づくり」として継続 → 体型維持・ストレス発散のメリットを伝える
- 自分で計画を立てさせる → 「どんな運動なら続けられそう?」と相談する
5. ゲーム感覚で運動を楽しむ工夫

- シールチャレンジ → 運動をした日はカレンダーにシールを貼る(目標達成でご褒美!)
- 親子ランキング → 1週間で何回できるか競争!(縄跳び、スクワットなど)
- くじ引き運動 → 運動メニューを紙に書いてくじ引きで決める(何が出るかワクワク!)
ゲーム感覚を取り入れることで、楽しみながら運動習慣をつけることができます!
6. 忙しい親でもできる簡単運動習慣

すきま時間でできる「時短運動」:
- 朝の3分間ストレッチ(子どもと一緒に体をほぐす)
- 通学・通勤時にエレベーターを使わず階段を使う
- テレビのCM中にスクワット10回
親子で楽しめる簡単運動:
- キャッチボール:「3回連続でキャッチできるかな?」とゲーム感覚で楽しむ
- ダンス:好きな音楽に合わせてダンスをする(YouTubeのダンス動画もおすすめ)
- ヨガ:夜寝る前に親子でリラックスヨガ
7. 運動指導のポイント

- 子どもの個性や興味を尊重する(嫌がる運動を無理強いしない)
- 「過程」を褒める(結果だけでなく、努力や成長を認める)
- 失敗を責めず、「どうしたらできる?」と考えさせる
- 親自身が運動を楽しむ姿を見せる(親が楽しめば、子どもも楽しむ)
8. 親ができるサポート

- 「やりなさい!」ではなく「一緒にやろう!」の姿勢
- 成功体験を積ませる → できたことをしっかり褒める
- 子どもが主役!自分で決めさせる → どんな運動をするか選ばせる
9. まとめ:今日から始める運動習慣!
運動は、子どものやる気を引き出し、目標に向かって努力する力・協調性・忍耐力 など、さまざまな非認知能力を育む重要な要素です。
しかし、大切なのは「特別なトレーニングをすること」ではなく、日常の中で楽しく体を動かす習慣をつくることです。
まずは 1日5分 から!
親子で一緒にできる運動を取り入れて、楽しみながら続けていきましょう。
「少しずつ、楽しく続けること」 こそが、子どもの成長につながります。
「運動×非認知能力」で、子どもの未来をもっと豊かに! まずは今日から、できることを一緒に始めてみませんか?
おすすめ記事 (非認知能力の育成シリーズ)
- 「なぜ非認知能力が重要なのか?親ができる3つのこと」(基本概念)
- 「遊びで伸ばす非認知能力|3歳からの簡単アクティビティ5選」(実践編)
- 「やる気を引き出す「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の効果的な組み合わせ方」(モチベーション編)
- 「運動×非認知能力:子どものやる気を引き出す運動習慣の作り方」(運動分野)→この記事
- 「家庭でできる音楽教育と非認知能力の育成」(音楽分野)
- 「アート体験&鑑賞で子どもの才能開花!親子で育む非認知能力」(芸術分野)
- 「自然体験で非認知能力を伸ばす!親子で楽しめるアウトドア学習」(自然分野)