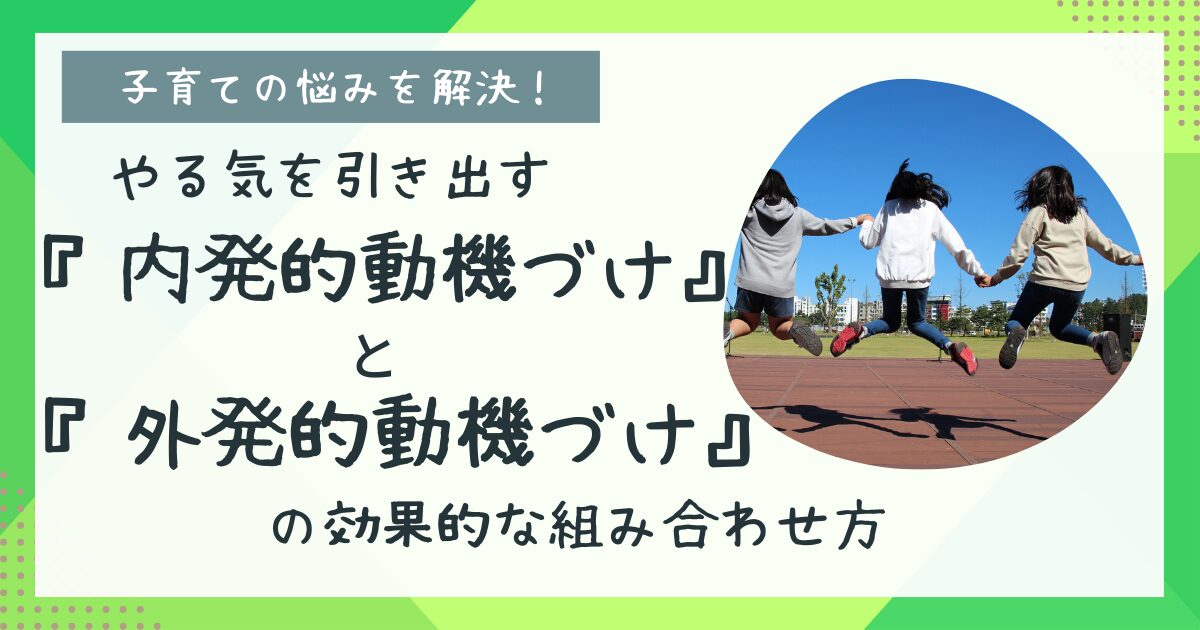
子育ては、私たち親にとって最もやりがいのある仕事の一つですが、同時に多くの悩みや課題も伴います。
特に、子どもたちの「やる気」を引き出し、自ら学ぶ力を育むことは、親にとって永遠のテーマと言えるでしょう。
「うちの子、どうしたらやる気になるのかしら…」
そんな悩みを抱えるあなたは、もしかしたらこの記事が解決の糸口になるかもしれません。
近年、心理学や教育学の研究が進み、子どもの動機づけに関するメカニズムが明らかになってきました。
この記事では、エビデンスに基づいた最新の知見を交えながら、子育てにおける動機づけの二つの側面、「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」に焦点を当て、その効果的な活用方法について解説していきます。
なぜ、子どもの「やる気」を引き出すことが大切なの?

子どもは、生まれながらにして学ぶ力を持っています。
しかし、その力を最大限に引き出すためには、周囲の大人たちのサポートが不可欠です。
子どもが自ら「やりたい!」という気持ちを持つことができれば、困難に立ち向かう力や、新しいことを学ぶ楽しさを身につけることができます。
「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」って何?
子どもの動機づけには、大きく分けて「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の2つがあります。
- 内発的動機づけ:子ども自身の興味や好奇心、探求心から生まれる「やりたい!」という気持ちです。
- 外発的動機づけ:報酬や賞罰、親からの期待など、外部からの刺激によって生まれる「やらなければ」という気持ちです。
内発的動機づけの重要性

内発的動機づけによって行動する子どもは、困難に立ち向かう力や、新しいことを学ぶ楽しさを身につけることができます。
最新の研究では、内発的動機づけが子どもの創造性や問題解決能力、自律性を高めることが示されています。
また、内発的動機づけは、長期的な学習意欲や学力向上にもつながることが明らかになっています。
外発的動機づけの功罪

外発的動機づけは、一時的に子どもの行動を促すために有効な手段ですが、過度に依存すると、子ども自身の内発的な動機づけを損なう可能性があります。
報酬を与えることのデメリットとしては、子どもが報酬を得るためだけに努力するようになり、本来の楽しさや価値を見失ってしまうことが挙げられます。
また、罰を与えることは、子どもの自尊心を傷つけ、反発心を招く可能性があります。
効果的な動機づけ戦略

子育てにおいては、内発的動機づけと外発的動機づけのバランスを保ちながら、子どもの成長をサポートすることが重要です。
内発的動機づけを育むためのポイント!
- 子どもの興味や関心をよく観察し、それを伸ばせるような環境を提供する。
- 子どもの「なぜ?」「どうして?」という質問に丁寧に答える。
- 子どもが自分で考えて行動できる機会を与える。
- 結果だけでなく、プロセスを褒める。
- 失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気を作る。
外発的動機づけを用いる場合の注意点
- 報酬は、子どもの努力や行動を具体的に評価する形で与える。
- 罰を与える場合には、子どもの気持ちに寄り添い、なぜその行動が問題なのかを丁寧に説明する。
- 外発的動機づけはあくまで一時的な手段であり、徐々に内発的動機づけへと移行できるように促す。
事例紹介
以下に、内発的動機づけと外発的動機づけを効果的に活用した事例と、やってはいけない事例を紹介します。
効果的な事例

事例1:算数嫌いを克服!ゲームで楽しく学ぶ
小学3年生のC君は、算数が苦手。特に、計算問題が嫌いで、宿題のプリントを見るのも嫌がるほどでした。 お母さんは、C君に無理強いするのではなく、算数を好きになるきっかけを作りたいと考えました。
そこで、お母さんはC君と一緒に、算数を使ったゲームをすることにしました。 「すごろくゲーム」や「お買い物ゲーム」など、C君が興味を持ちそうなゲームを選び、遊びながら算数の基礎を学べるように工夫しました。
最初は乗り気でなかったC君も、ゲームが始まると夢中に。 サイコロを振ったり、お金を計算したりするうちに、自然と算数に触れる機会が増えました。 お母さんは、C君がゲームに勝つたびに、「すごいね!よくできたね!」と褒め、C君の自信をつけました。
数週間後、C君は算数の宿題に以前よりも積極的に取り組むようになりました。 計算問題も、ゲームで学んだことを応用して、スムーズに解けるようになりました。 お母さんは、「C君、算数が好きになったね!」とC君の成長を喜びました。
この事例からわかること
- 内発的動機づけのポイント:C君が「算数=つまらない」というイメージを持っていたのを、ゲームを通して「算数=楽しい」というイメージに変えました。
- 外発的動機づけのポイント:ゲームに勝つたびに褒めることで、C君の努力を認め、達成感を味わわせました。
事例2:読書好き少女、好奇心を刺激する図書館通い
小学5年生のDさんは、読書が大好き。 お母さんは、Dさんの読書好きをさらに伸ばしたいと考えました。
そこで、お母さんはDさんと一緒に、図書館に行くことにしました。 図書館には、様々なジャンルの本があり、Dさんは目を輝かせていました。 お母さんは、Dさんに「好きな本を自由に選んでいいよ」と声をかけました。
Dさんは、普段読まないジャンルの本にも興味を持ち、何冊か選びました。 お母さんは、Dさんが選んだ本について、「この本はどんな話かな?」「この本の作者はどんな人かな?」と質問し、Dさんの好奇心を刺激しました。
数週間後、Dさんは図書館で借りた本を読み終え、感想文を書きました。 お母さんは、Dさんの感想文を読み、「〇〇ちゃんの感想、とても面白かったよ!」と褒めました。
この事例からわかること
- 内発的動機づけのポイント:Dさんの「本を読みたい」という内発的な動機を尊重し、お母さんは自由に本を選べる環境を提供しました。
- 外発的動機づけのポイント:感想文を褒めることで、Dさんの努力を認め、達成感を味わわせました。
やってはいけない事例

事例3:テストで良い点を取ったらゲームを買ってあげる
小学4年生のE君は、ゲームが大好き。 お母さんは、E君に「テストで良い点を取ったらゲームを買ってあげる」と約束しました。
E君は、ゲームを買ってもらうために、テスト勉強を頑張りました。 しかし、テストが終わると、すぐにゲームに夢中になり、勉強のことなど忘れてしまいました。
次のテスト前になると、E君はまた「ゲームを買ってほしい」とお母さんにせがみました。 お母さんは、「またテストで良い点を取ったら買ってあげる」と言いました。
E君は、ゲームのためだけに勉強するようになり、勉強自体を楽しむことができませんでした。
この事例からわかること
- 外発的動機づけの誤った使い方:報酬(ゲーム)を目的に勉強させることは、一時的に効果があるかもしれませんが、子ども自身の内発的な学習意欲を育むことはできません。
- 長期的な影響:報酬に依存した勉強は、テストが終わるとやる気を失い、継続的な学習習慣を身につけることができません。
E君のケース:どのように対応すればよかったのか?
お母さんは、E君にゲームを与えることを報酬ではなく、目標達成の「ご褒美」として与えるべきでした。
例えば、
- 目標設定:E君と一緒に、次のテストで達成したい目標を具体的に決める。(例:算数のテストで80点以上取る)
- 努力の過程を重視:目標達成に向けて、E君がどのように努力したのか、プロセスを具体的に褒める。(例:「毎日、算数の宿題を頑張っているね」「難しい問題にも粘り強く取り組んでいるね」)
- ご褒美:目標を達成したら、約束通りゲームを買ってあげる。
- 内発的動機づけの促進:ゲームで遊ぶ中で、算数の面白さや論理的思考力を伸ばせるような要素を取り入れる。(例:算数パズルゲーム、シミュレーションゲーム)
このように、目標設定、努力の可視化、達成感、そして内発的動機づけを組み合わせることで、E君はゲームを目標達成の「ご褒美」として捉え、自ら学ぶ意欲を高めることができたでしょう。
事例4:ピアノの練習を強制する
小学2年生のFちゃんは、ピアノを習っています。 お母さんは、Fちゃんに「毎日1時間ピアノの練習をしなさい」と強制しました。
Fちゃんは、毎日嫌々ながらピアノの練習をしていました。 練習中に間違えると、お母さんに厳しく叱られ、ピアノが嫌いになってしまいました。
発表会が近づくと、お母さんはFちゃんに「もっと練習しなさい」とプレッシャーをかけました。 Fちゃんは、発表会でうまく演奏することができず、自信を失ってしまいました。
この事例からわかること
- 内発的動機づけの阻害:子どもの興味や関心を無視して、練習を強制することは、内発的な学習意欲を阻害する可能性があります。
- 悪影響:プレッシャーをかけすぎると、子どもは自信を失い、学習自体を嫌いになってしまうことがあります。
Fちゃんのケース:どのように対応すればよかったのか?
お母さんは、Fちゃんにピアノを強制するのではなく、楽しむきっかけを与えるべきでした。
例えば、
- 目標設定:Fちゃんと一緒に、ピアノを通してどんなことをしたいか、目標を話し合う。(例:好きな曲を弾けるようになりたい、友達と合奏したい)
- 練習内容の工夫:Fちゃんのレベルに合った教材を選び、練習内容を工夫する。(例:好きな曲の一部分だけを練習する、リズムに合わせて体を動かす)
- 成功体験:Fちゃんが少しでも上達したら、具体的に褒める。(例:「〇〇ちゃん、このフレーズが前よりずっと上手になったね」「〇〇ちゃんの演奏、とても感動したよ」)
- 発表会へのサポート:発表会に向けて、Fちゃんの気持ちに寄り添い、励ます。(例:「緊張するかもしれないけど、〇〇ちゃんなら大丈夫だよ」「練習の成果を出すことができれば、自信につながるよ」)
このように、目標設定、練習内容の工夫、成功体験、そして精神的なサポートを組み合わせることで、Fちゃんはピアノを「楽しい」と感じ、自ら練習する意欲を高めることができたでしょう。
まとめ
子育ては、子どもたちの未来を育む重要な営みです。
エビデンスに基づいた動機づけ戦略を活用することで、子どもたちの内発的な動機づけを育み、自ら学び、成長する力を高めることができます。
この記事が、子育てに携わる皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
子育ては、試行錯誤の連続です。うまくいかないことや悩むこともたくさんあるでしょう。
でも、子どもの成長を信じて、温かく見守ることが何よりも大切です。
おすすめ記事 (非認知能力の育成シリーズ)
- 「なぜ非認知能力が重要なのか?親ができる3つのこと」(基本概念)
- 「遊びで伸ばす非認知能力|3歳からの簡単アクティビティ5選」(実践編)
- 「やる気を引き出す「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の効果的な組み合わせ方」(モチベーション編)→この記事
- 「運動×非認知能力:子どものやる気を引き出す運動習慣の作り方」(運動分野)
- 「家庭でできる音楽教育と非認知能力の育成」(音楽分野)
- 「アート体験&鑑賞で子どもの才能開花!親子で育む非認知能力」(芸術分野)
- 「自然体験で非認知能力を伸ばす!親子で楽しめるアウトドア学習」(自然分野)